あわてない、あわてない・・・
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
英語検定協会主催の研修会に参加します。
2013年11月1日(金)に函館市で
開催予定の「英語でつながろう 2013
函館」に役立つ情報と人脈を入手します。
参加される方で私を見かけたらシカトしな
いでください。
研修会後、軽く一杯ひっかけてJRで戻り
ます。
事故にまきこまれないことを願いつつ・・・。

2013年11月1日(金)に函館市で
開催予定の「英語でつながろう 2013
函館」に役立つ情報と人脈を入手します。
参加される方で私を見かけたらシカトしな
いでください。
研修会後、軽く一杯ひっかけてJRで戻り
ます。
事故にまきこまれないことを願いつつ・・・。
PR
昨日、附属中学校の福留先生の授業を参観させていただきました。
この授業ではタブレットを使いました。
6人前後で構成されたグループが、座ったり立ったり、机もイス
もないスペースで、まるで、カメラマンとキャスターになったよ
うに、メンバーを取材していました。
タブレットの活用は、まだ5回目とのこと。子どもたちの吸収は
早く、器用に使いこなしていました。
先日、アップル社がタブレットを教科書に変わるものとして紹介
していました。スティーブン・ジョッブズ氏の意を継いでのもの。
初等中等教育視学官である太田光春氏は、「教師は20年後の世
界に目をむけなくてはいけない」と先日の講演会で指摘しており
ました。
英語はコミュニケーションのツールの1つです。
スマートフォンでコミュニケーション能力が高まるわけではなく、
どんなに便利な機能が備わったとしても、根っこにあるのは「人
と人をつなげること」の1つのツールです。
まるでカルタをするように円座になり遊びのように学ぶ、または、
STVのテレビカメラ(取材に来ていました)をものともせずに、
立ったまま円陣を組むように、タブレットに顔を向けて、"Did
you study English yesterday?"または"I studied at
eight."と話す姿、それを温かく見守る子どもたちの姿が印象的
でした。
タブレットを使う前には、教室の仲間とのきさくな人間関係が
大前提です。この学級はとても良い感じでした。
タブレットの機能について、自分なりの経験からここでお話しし
たい点があります。
ホームページを立ち上げるときに、QHM(クイック ホーム
ページ メーカー)というものを使いました。
この特徴は「初心者に優しい」に尽きます。文字による説明に
加えて、インターネット上でビデオを見ることができます。
これから自分がやろうとするところの、実演を見ておくことが
できるのです。
これほど、わかりやすいものは他には見あたりませんでした。
この機能はタブレットで可能となります。
目標とする部分に絞って、各自がモデルを参考に学習できます。
また、過去の自分の発音と現在のものを比較し、上達度を確か
めることも可能です。
授業では、数人のタブレットを紹介し、全体のものとしていま
した。
子どもたちの振り返りでは、「目標は、『自信を持って話す』
でした。目(タブレット)を見て話すことはできましたが、
声が小さかったです。次回は自信を持って話せるようにしたい
です」や「Didを使うところをDoを使って言っていました。次
には間違わないで言えるようにしたいです」などなど。
自分や友人が話したものがタブレットで確認でき、上記のよう
な振り返りを可能にしていました。
1つの未来に向けた試みとして、附属中の挑戦は興味深いもの
がありました。
およそ30年で、ガリ版と鉄筆、ボールペン原紙、電子和文タ
イプライター、ワープロ(かつては、三行表示されただけで
産業革命と言われていましたが・・・)、パソコン。
いよいよ電子教科書の時代が来るのかな・・・と感じました。
授業の記録はビデオにとっております。プライバシー等の関係
に配慮する必要がありますので、視聴を希望される方は直接
安達までご連絡願います。
ktadachi@nifty.com
090-9512-7330




この授業ではタブレットを使いました。
6人前後で構成されたグループが、座ったり立ったり、机もイス
もないスペースで、まるで、カメラマンとキャスターになったよ
うに、メンバーを取材していました。
タブレットの活用は、まだ5回目とのこと。子どもたちの吸収は
早く、器用に使いこなしていました。
先日、アップル社がタブレットを教科書に変わるものとして紹介
していました。スティーブン・ジョッブズ氏の意を継いでのもの。
初等中等教育視学官である太田光春氏は、「教師は20年後の世
界に目をむけなくてはいけない」と先日の講演会で指摘しており
ました。
英語はコミュニケーションのツールの1つです。
スマートフォンでコミュニケーション能力が高まるわけではなく、
どんなに便利な機能が備わったとしても、根っこにあるのは「人
と人をつなげること」の1つのツールです。
まるでカルタをするように円座になり遊びのように学ぶ、または、
STVのテレビカメラ(取材に来ていました)をものともせずに、
立ったまま円陣を組むように、タブレットに顔を向けて、"Did
you study English yesterday?"または"I studied at
eight."と話す姿、それを温かく見守る子どもたちの姿が印象的
でした。
タブレットを使う前には、教室の仲間とのきさくな人間関係が
大前提です。この学級はとても良い感じでした。
タブレットの機能について、自分なりの経験からここでお話しし
たい点があります。
ホームページを立ち上げるときに、QHM(クイック ホーム
ページ メーカー)というものを使いました。
この特徴は「初心者に優しい」に尽きます。文字による説明に
加えて、インターネット上でビデオを見ることができます。
これから自分がやろうとするところの、実演を見ておくことが
できるのです。
これほど、わかりやすいものは他には見あたりませんでした。
この機能はタブレットで可能となります。
目標とする部分に絞って、各自がモデルを参考に学習できます。
また、過去の自分の発音と現在のものを比較し、上達度を確か
めることも可能です。
授業では、数人のタブレットを紹介し、全体のものとしていま
した。
子どもたちの振り返りでは、「目標は、『自信を持って話す』
でした。目(タブレット)を見て話すことはできましたが、
声が小さかったです。次回は自信を持って話せるようにしたい
です」や「Didを使うところをDoを使って言っていました。次
には間違わないで言えるようにしたいです」などなど。
自分や友人が話したものがタブレットで確認でき、上記のよう
な振り返りを可能にしていました。
1つの未来に向けた試みとして、附属中の挑戦は興味深いもの
がありました。
およそ30年で、ガリ版と鉄筆、ボールペン原紙、電子和文タ
イプライター、ワープロ(かつては、三行表示されただけで
産業革命と言われていましたが・・・)、パソコン。
いよいよ電子教科書の時代が来るのかな・・・と感じました。
授業の記録はビデオにとっております。プライバシー等の関係
に配慮する必要がありますので、視聴を希望される方は直接
安達までご連絡願います。
ktadachi@nifty.com
090-9512-7330
中部高校公開授業では以下の5名の先生が公開してくれました。
3教時
コミュニケーション英語Ⅰ 浜谷教諭(1年)(ビデオ記録有り)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
コミュニケーション英語Ⅱ 相馬教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
コミュニケーション英語Ⅱ 大塚教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
4教時
コミュニケーション英語Ⅰ 白鳥教諭(1年)(ビデオ記録あり)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
コミュニケーション英語Ⅱ 竹内教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
自分はビデオ撮影のため以下の2つの授業しか参観できませんでした。
なお、2つの授業はブルーレイディスクに記録してます。
貸し出し可能ですので、ご連絡願います。
安達
ktadachi@nifty.com
090-9512-7330
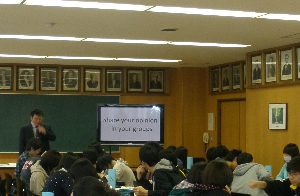
コミュニケーション英語Ⅰ 浜谷教諭(1年)(ビデオ記録有り)では、
Warm Up Activity
You should say...
Have you ever had any pets?
If he / she says "Yes"
Please tell me what pets you have had.
If he / she says "No"
Please tell me what pets you want to have.
Please ask each other in a circle.
A→B→C→D→E→A...
Name
Yes, he / she has.
He / She has had ....................
No, he / she hasn't had.
He / She wants to have...............
上記の活動を5分間。
続いてアンケート結果を公表。(集中は高かったです。意外にも猫は3位。)
No.1 Dogs
No.2 Gold Fish
No.3 Cats
この後、ペットの死に関しての話題に移りますが、自然な移行でした。
電子黒板の使いどころも良かったです。
続いて、本文についての理解とリーディング練習。
そして、結びは以下のような意見交換。
In this story...
The boy will have to make a decision whether to ask the veterinarian to euthanize his cat or not.
*veterinarian :doctor for animals *enthanize :kill without pain
Thinking
If you find that your pets cannot live any longer, do you want to euthanize them, or not?
Why? Or why not?
Yes, I want to do so. / No, I don't want to do so.
Why / Why not?
Share your opinion with group members.
Name
Yes, he / she wants to do so. No, he / she doesn't want to do so.
Why / Why not?
4教時
コミュニケーション英語Ⅰ 白鳥教諭(1年)(ビデオ記録あり)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
挨拶・単語帳(15分)
・単語帳DUO3.0の2文の小テスト。
・次回の単語の確認・発音練習。新出単語を用いて架空の文を作らせ、ペアワーク。
前時の復習(9分)
本文の復習・理解(11分)
Today's question:Will you let your pet die die naturally or give it an injection to put it to sleep? Why?
意見交換
Homework:What do you want to teach your future children as a lesson?
補助シート
Activity
1 Write one lesson you learned from your parents or experiences?
2 Why do you think it is important?
3 What do you want to teach your future children as a lesson?
4 Why do you want teach it?
生徒はペアやグループで意見交換していました。
上の2つの授業はともに生徒に英語を使わせる場面を設定し、期間巡視でアドバイスや
理解度の確認をしていました。
個人的な感想としては、随所に「発信するための英語力」を育む工夫を感じました。
ただ、大勢の先生がいたためか、声が小さい印象を持ちました。
発表している生徒が座っている場面もあり、どの子が発表しているのかわからないとこ
ろもありました。発表者がわかると、聞いている生徒もわかりやすいと思いますす。
高校へ進む前に、中学校では、まずは、大きな声で相手にわかるように伝えようとする
気持ちを育てたいです。
簡単な日常会話を毎回取り入れられると、高校での活動へのステップとなります。
中英研の課題として会員に鼓舞していきます。
午後の学習会から・・・。
all Englishについて
Q:導入期(4月・5月)はどのように?
A:教科担任の持ち味にもよるが4月からならしていった。
ゆっくりめの丁寧な進め方で。
Q:センター試験などの扱いは?
A:結果は特に下がっていない。自分で考えて書くことが力になっているかも。
Q定期テストではどんな問題を?
A:和訳は出さない。パフォーマンス評価、一斉writing、インタビュー(7月、12月、2月)などを
取り入れている。
(筆者の記憶が定かではありませんが)インタビューは①発音・表現(4会場で50分かけて)②プレゼ
ンテスト③パワーポイントによるプレゼン(1人4~5分。4会場で)
Q:教科書PRO-VISIONについて(毎回このような展開を?)
A:すべての題材ではできないが、考えさせ、英語を使わせる、身振りや手振りを使っても伝
える力を育てるようにしている。
Q:自分の意見を書かせて、発表させていた。文法上のミスも見かけたが、生徒の自己チェックでは
間違いがそのままになってしまう恐れがある。生徒数が10人前後なら1人で可能と思うが、40人
ちかい場合は無理だと思う。どのようにしているのか?
A:最終的には正しい英語に近づけていく。正しい言葉や文法の正確さを強調すると、生徒は言えな
くなる。Communication 2の時は「言う」方に重きを置いている。
書かせた文章の誤りのチェックについては2人のALTに協力してもらっている。
などなど、活発な意見交流がありました。
前日のレセプションでは、授業者が参加者に辛口コメントをどんどん言って下さいとおっしゃってました。
中部高校の先生は熱い情熱の持ち主が多いと感銘を受けました。
本当にお疲れ様でした。
学ばれたことを子どもたちに返してあげてください!
中学校でも、記録したビデオを中学1年生に見せて、高校の授業の現実を知らせて、さらに、英語力を向上
させたいです。
3教時
コミュニケーション英語Ⅰ 浜谷教諭(1年)(ビデオ記録有り)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
コミュニケーション英語Ⅱ 相馬教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
コミュニケーション英語Ⅱ 大塚教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
4教時
コミュニケーション英語Ⅰ 白鳥教諭(1年)(ビデオ記録あり)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
コミュニケーション英語Ⅱ 竹内教諭(2年)
使用教科書 PRO-VISION ENGLISH COURSE Ⅱ 桐原書店発行 Duo3.0(アイシーピー)
題材 Lesson 6 "A Man Who Saved the World"
自分はビデオ撮影のため以下の2つの授業しか参観できませんでした。
なお、2つの授業はブルーレイディスクに記録してます。
貸し出し可能ですので、ご連絡願います。
安達
ktadachi@nifty.com
090-9512-7330
コミュニケーション英語Ⅰ 浜谷教諭(1年)(ビデオ記録有り)では、
Warm Up Activity
You should say...
Have you ever had any pets?
If he / she says "Yes"
Please tell me what pets you have had.
If he / she says "No"
Please tell me what pets you want to have.
Please ask each other in a circle.
A→B→C→D→E→A...
Name
Yes, he / she has.
He / She has had ....................
No, he / she hasn't had.
He / She wants to have...............
上記の活動を5分間。
続いてアンケート結果を公表。(集中は高かったです。意外にも猫は3位。)
No.1 Dogs
No.2 Gold Fish
No.3 Cats
この後、ペットの死に関しての話題に移りますが、自然な移行でした。
電子黒板の使いどころも良かったです。
続いて、本文についての理解とリーディング練習。
そして、結びは以下のような意見交換。
In this story...
The boy will have to make a decision whether to ask the veterinarian to euthanize his cat or not.
*veterinarian :doctor for animals *enthanize :kill without pain
Thinking
If you find that your pets cannot live any longer, do you want to euthanize them, or not?
Why? Or why not?
Yes, I want to do so. / No, I don't want to do so.
Why / Why not?
Share your opinion with group members.
Name
Yes, he / she wants to do so. No, he / she doesn't want to do so.
Why / Why not?
4教時
コミュニケーション英語Ⅰ 白鳥教諭(1年)(ビデオ記録あり)
使用教科書 Prominence English Ⅰ 東京書籍発行
題材 Option 2 The Boys and the Cat
挨拶・単語帳(15分)
・単語帳DUO3.0の2文の小テスト。
・次回の単語の確認・発音練習。新出単語を用いて架空の文を作らせ、ペアワーク。
前時の復習(9分)
本文の復習・理解(11分)
Today's question:Will you let your pet die die naturally or give it an injection to put it to sleep? Why?
意見交換
Homework:What do you want to teach your future children as a lesson?
補助シート
Activity
1 Write one lesson you learned from your parents or experiences?
2 Why do you think it is important?
3 What do you want to teach your future children as a lesson?
4 Why do you want teach it?
生徒はペアやグループで意見交換していました。
上の2つの授業はともに生徒に英語を使わせる場面を設定し、期間巡視でアドバイスや
理解度の確認をしていました。
個人的な感想としては、随所に「発信するための英語力」を育む工夫を感じました。
ただ、大勢の先生がいたためか、声が小さい印象を持ちました。
発表している生徒が座っている場面もあり、どの子が発表しているのかわからないとこ
ろもありました。発表者がわかると、聞いている生徒もわかりやすいと思いますす。
高校へ進む前に、中学校では、まずは、大きな声で相手にわかるように伝えようとする
気持ちを育てたいです。
簡単な日常会話を毎回取り入れられると、高校での活動へのステップとなります。
中英研の課題として会員に鼓舞していきます。
午後の学習会から・・・。
all Englishについて
Q:導入期(4月・5月)はどのように?
A:教科担任の持ち味にもよるが4月からならしていった。
ゆっくりめの丁寧な進め方で。
Q:センター試験などの扱いは?
A:結果は特に下がっていない。自分で考えて書くことが力になっているかも。
Q定期テストではどんな問題を?
A:和訳は出さない。パフォーマンス評価、一斉writing、インタビュー(7月、12月、2月)などを
取り入れている。
(筆者の記憶が定かではありませんが)インタビューは①発音・表現(4会場で50分かけて)②プレゼ
ンテスト③パワーポイントによるプレゼン(1人4~5分。4会場で)
Q:教科書PRO-VISIONについて(毎回このような展開を?)
A:すべての題材ではできないが、考えさせ、英語を使わせる、身振りや手振りを使っても伝
える力を育てるようにしている。
Q:自分の意見を書かせて、発表させていた。文法上のミスも見かけたが、生徒の自己チェックでは
間違いがそのままになってしまう恐れがある。生徒数が10人前後なら1人で可能と思うが、40人
ちかい場合は無理だと思う。どのようにしているのか?
A:最終的には正しい英語に近づけていく。正しい言葉や文法の正確さを強調すると、生徒は言えな
くなる。Communication 2の時は「言う」方に重きを置いている。
書かせた文章の誤りのチェックについては2人のALTに協力してもらっている。
などなど、活発な意見交流がありました。
前日のレセプションでは、授業者が参加者に辛口コメントをどんどん言って下さいとおっしゃってました。
中部高校の先生は熱い情熱の持ち主が多いと感銘を受けました。
本当にお疲れ様でした。
学ばれたことを子どもたちに返してあげてください!
中学校でも、記録したビデオを中学1年生に見せて、高校の授業の現実を知らせて、さらに、英語力を向上
させたいです。
明後日(2月17日(金)に、中部高校で「英語研究に
関わる研究協議会」が開催されます。
講師は昨年(2月18日)も講演していただいた太田氏
です。昨年の資料を載せました。ぜひ、ご一読してから
講演をお聞き下さい。理解がより深まると思います。
「コミュニケーション能力の育成を図る授業の創造」
~自律した学習者の育成を目指して~
文部科学省初等中等教育局視学官 太田光春
1 学校教育、外国語教育の使命
(1)学校教育法第30条2項で求められていること
知識基盤社会の到来
(2)学習指導要領で求められていること
ア 目標
イ 科目構成
ウ 第3款
2 言語(英語)を取り巻く環境、世界の情勢
(1)世界の状況
ア 中国、韓国
イ EU
(2)日本の状況
ア EFL
EFLだからこそ必要なこと
イ 科学技術の進歩
3 日本の英語教育の諸問題
(1)学習指導要領の求める力と指導の実態との乖離
ア 使命・目的の認識における乖離
イ 「コミュニケーション能力」の解釈における乖離
ウ 文法のとらえ方や文法指導の在り方に関する考え方の乖離
エ 授業の主体についての考え方の乖離
(2)Exposure,Experience & Interactionの不足
(例)水泳、運転、楽器演奏
(3)英語を理解することに関する誤解
ア Ambiguity Toleranceの必要性
イ Inferenceの必要性
ウ Communication Strategiesの必要性
(4) 生徒が一人でできること、教師がいるから効果的にできること、
他の生徒がいるからできること、ALTや留学生がいるからできること
についての整理不足
(5) 主体的に学習する生徒を育てる視点から家庭学習を考えていな
い可能性
(6) 「指導と評価の一体化」という視点を踏まえたテスティングの
改善が不十分である可能性
(7) 学校が組織として機能することの必要性
4 第3款の4について
(1)求めるもの
ア Comprehensible Input
イ Exposure,Experience(Language use & Interaction)
ウ Rapport
(2)日本語の使用について
ア 文法の扱いについて
イ ハンドアウトについて
(3)教師に求められている英語
ア 授業を展開する英語
イ 音声モデル
ウ 理解を助ける英語、確認する英語
エ 言語活動を成功に導くための英語
オ ほめる英語、動機付けをする英語
(4) 学習の主体は生徒
(5) 言語活動について
ア 学習的な活動
イ コミュニケーションを図る活動
ウ 学習的な活動とコミュニケーションを活動のバランス
5 その他
(1) 可能性を信じること
(2) 学び続けること
(3) コミュニケーション体験と人を思いやる気持ち・自己有用感
(4) 交響曲と異文化理解
(5) Comparison,Competion & Synergy, Collaboration
6 補足
(1) 高等学校外国語移行期間中の留意点について
留意点の1つは、現行学習指導要領下においても新学習指導要領第3款の4
の趣旨を踏まえてできるだけ速やかに「英語で行うことを基本とする」授業
になるよう組織的に取り組むことである。
新学習指導要領の外国語の内容及び専門学科の「英語」については平成25
年度から年次進行で実施されることになっており、先行実施はされない。
しかしながら、「授業は英語で行うことを基本とする」という第3款の4の
規定は、そのような指導に慣れていない教員にとっては、平成25年度から
突然始められるものではない。
平成25年度から円滑に実施するためには、現行学習指導要領下においても
できるだけ授業を英語で行うようにすることが肝要である。
その際大切なことは、「生徒の理解の程度に応じた英語を用いる」ことである。
生徒の理解の程度を無視した英語では、生徒の自信や学習意欲を損なってしま
う可能性が高いからである。授業では、生徒が理解できているかを常に確認し
ながら、次のような英語を使うようになる。
ア 授業を展開する英語
あいさつや生徒を授業に引き込むためのsmall Talkを含めて、指示をしたり、
説明をしたりするなど授業を展開するために使う英語のことである。日常的に
使うことになるので、すぐに習熟できるものである。
イ 音声モデルとしての英語
生徒が独力で英語の音声に習熟することは容易なことではない。一方、教員
による手本や指導があれば、さほど難しいことではない。教員は自ら手本を
示したり音声教材を用いたりしながら、個々の単語の発音だけでなく、英語
のリズムやイントネーション、音の脱落や連結などについて指導をする必要
がある。
英語の母語話者は、意味が分かりさえすれば外国語として英語を話す人の音
声的な誤りを指摘したり訂正したりすることはしない。したがって、調音の
方法や場所を示しながら適切な音声モデルを提供することは、教員の大切な
役割だと言える。
ウ 理解を助ける英語、確認する英語
これは、聞いたり読んだりした内容について、目的に応じた理解ができてい
るかどうか確認したり、理解を促進したりするために使う英語である。
説明のためのTeacher Talk や WH疑問文などを用いた質問・応答がこれに
当たる。
エ 言語活動を成功に導くための英語
学習の主体は生徒であり、授業においては教員以上に生徒が英語を使う機会
がなければならない。そのためには、適切な言語活動、特に、コミュニケー
ションを図る言語活動が授業の中心となるような指導が行われなければなら
ない。
教員には、教科書の内容を素材として、その素材に適した言語活動を工夫す
ることが求められる。必要に応じて、文法を言語活動と効果的に関連づけて
指導することも求められる。
これらを効果的に行うための一連の準備を一人の教員が担うことは大変であ
る。同じ学年を担当する教員が協力して行うことが大いに期待される。
言語活動をさせる際には、生徒が思いつかなくて活動が行き詰まっている英
語表現を提示するなど、つまづきを乗り越えられるよう適切な助言をして、
活動に従事しているすべての生徒が達成感を味わうことができるように配慮
しなければならない。毎時間繰り返される言語活動が生徒にとって失敗の連
続になってしまうようでは、英語学習への動機付けができないからである。
オ ほめる英語、動機付けをする英語
どんなに学習が進んでも、自分の英語力に自信を持てる生徒は少ない。なぜなら、
英語は外国語であり、進歩の状況が自分ではわかりにくいものだからである。
そのような学習者に対して動機付けをし、その動機を維持させるためには、生
徒が英語を使ってできたことやできるようになったことを明らかにして、ほめ
る必要がある。そのため、教員には意図的かつ積極的にmotivation feedback
をすることが求められる。
(2) 授業の実践に当たって気をつけてほしこと
ア 生徒の理解の程度に応じた英語を使うこと
生徒の理解を超えた英語は、どれだけ聞かせても英語によるコミュニケーショ
ン能力の育成にはつながらない。言語習得に必要な適切なインプットにならな
いからである。
教員は、生徒の表情や質問に対する応答から、理解の状況を把握し、必要に応
じて、話す速度を落としたり、優しい表現に言い換えたり、例示をしたり、黒
板に絵を描いたり、実物を示したりするなどして、生徒が耳にした英語を推測
しながら概ね理解できるようにする必要がある。
理解に「あいまいさ」が残る場合には、不安に感じる生徒もいると思われる。
そのような生徒に対しては、外国語はあいまいさに耐えながら曖昧さを減じて
いく営みであるから心配しなくてもよいことを伝えて、安心させる必要がある。
また、仮に、日本語を聞いて英語が理解できたつもりになっても、それは英語
ではなく、日本語を理解しているに過ぎない場合が多いということも伝える必
要がある。英語を理解させるためには絶対に日本語が必要だという誤解が生じ
ないような指導が大切なのである。
イ 教員が話しすぎないこと
学習の主体は生徒である。「授業は英語で行うことを基本とする」とは言って
も、授業時間のほとんどを教員が話しているようでは、生徒が英語を使う場を
奪ってしまうことになる。授業には、生徒が、分かる英語に触れる機会
(exposure)と生徒がコミュニケーションの手段として英語を使う場合
(experience)がバランスよく盛り込まれていなければならない。
ウ 動機付けを意識した授業をすること
授業は動機付けの場、動機を持続させる場であるとも言える。本時の授業で、
生徒の学習意欲を喚起することができたのか、もしかしたら、意欲を減退させ
てはいないかという視点から授業を振り返り、必要な改善を図ることが求めら
れる。
エ 学習的な言語活動とコミュニケーションを図る言語活動のバランスを考え
ること
教員や音声教材を手本にして徹底的に音声練習をしたり、ディクテーションを
したりするなど英語そのものの改善を目的にした学習的な言語活動と、要約を
伝えたり自分の意見を述べたりするなど、英語を使ってコミュニケーションを
図ることを目的にした授業をバランスよく設ける必要がある。その割合は、生
徒の実態に応じて変えるべきものであり、一律に示すことはできない。
オ 親和関係を構築すること
コミュニケーション能力を育成する教室には親和関係が生まれる。また、親和
関係が存在しなければ、コミュニケーション能力の育成はうまくできない。
教員の英語に対する熱い思いや英語に接することの喜びを態度に示しながら、
生徒一人一人の学びを大切にする指導を持続することによって、教室に信頼と
尊敬が生まれる。
そのような教室には、失敗が許し合える雰囲気が生まれ、生徒の自発的な発言
を引き出しやすい環境になる。言語活動に最適な環境が創られるのである。

関わる研究協議会」が開催されます。
講師は昨年(2月18日)も講演していただいた太田氏
です。昨年の資料を載せました。ぜひ、ご一読してから
講演をお聞き下さい。理解がより深まると思います。
「コミュニケーション能力の育成を図る授業の創造」
~自律した学習者の育成を目指して~
文部科学省初等中等教育局視学官 太田光春
1 学校教育、外国語教育の使命
(1)学校教育法第30条2項で求められていること
知識基盤社会の到来
(2)学習指導要領で求められていること
ア 目標
イ 科目構成
ウ 第3款
2 言語(英語)を取り巻く環境、世界の情勢
(1)世界の状況
ア 中国、韓国
イ EU
(2)日本の状況
ア EFL
EFLだからこそ必要なこと
イ 科学技術の進歩
3 日本の英語教育の諸問題
(1)学習指導要領の求める力と指導の実態との乖離
ア 使命・目的の認識における乖離
イ 「コミュニケーション能力」の解釈における乖離
ウ 文法のとらえ方や文法指導の在り方に関する考え方の乖離
エ 授業の主体についての考え方の乖離
(2)Exposure,Experience & Interactionの不足
(例)水泳、運転、楽器演奏
(3)英語を理解することに関する誤解
ア Ambiguity Toleranceの必要性
イ Inferenceの必要性
ウ Communication Strategiesの必要性
(4) 生徒が一人でできること、教師がいるから効果的にできること、
他の生徒がいるからできること、ALTや留学生がいるからできること
についての整理不足
(5) 主体的に学習する生徒を育てる視点から家庭学習を考えていな
い可能性
(6) 「指導と評価の一体化」という視点を踏まえたテスティングの
改善が不十分である可能性
(7) 学校が組織として機能することの必要性
4 第3款の4について
(1)求めるもの
ア Comprehensible Input
イ Exposure,Experience(Language use & Interaction)
ウ Rapport
(2)日本語の使用について
ア 文法の扱いについて
イ ハンドアウトについて
(3)教師に求められている英語
ア 授業を展開する英語
イ 音声モデル
ウ 理解を助ける英語、確認する英語
エ 言語活動を成功に導くための英語
オ ほめる英語、動機付けをする英語
(4) 学習の主体は生徒
(5) 言語活動について
ア 学習的な活動
イ コミュニケーションを図る活動
ウ 学習的な活動とコミュニケーションを活動のバランス
5 その他
(1) 可能性を信じること
(2) 学び続けること
(3) コミュニケーション体験と人を思いやる気持ち・自己有用感
(4) 交響曲と異文化理解
(5) Comparison,Competion & Synergy, Collaboration
6 補足
(1) 高等学校外国語移行期間中の留意点について
留意点の1つは、現行学習指導要領下においても新学習指導要領第3款の4
の趣旨を踏まえてできるだけ速やかに「英語で行うことを基本とする」授業
になるよう組織的に取り組むことである。
新学習指導要領の外国語の内容及び専門学科の「英語」については平成25
年度から年次進行で実施されることになっており、先行実施はされない。
しかしながら、「授業は英語で行うことを基本とする」という第3款の4の
規定は、そのような指導に慣れていない教員にとっては、平成25年度から
突然始められるものではない。
平成25年度から円滑に実施するためには、現行学習指導要領下においても
できるだけ授業を英語で行うようにすることが肝要である。
その際大切なことは、「生徒の理解の程度に応じた英語を用いる」ことである。
生徒の理解の程度を無視した英語では、生徒の自信や学習意欲を損なってしま
う可能性が高いからである。授業では、生徒が理解できているかを常に確認し
ながら、次のような英語を使うようになる。
ア 授業を展開する英語
あいさつや生徒を授業に引き込むためのsmall Talkを含めて、指示をしたり、
説明をしたりするなど授業を展開するために使う英語のことである。日常的に
使うことになるので、すぐに習熟できるものである。
イ 音声モデルとしての英語
生徒が独力で英語の音声に習熟することは容易なことではない。一方、教員
による手本や指導があれば、さほど難しいことではない。教員は自ら手本を
示したり音声教材を用いたりしながら、個々の単語の発音だけでなく、英語
のリズムやイントネーション、音の脱落や連結などについて指導をする必要
がある。
英語の母語話者は、意味が分かりさえすれば外国語として英語を話す人の音
声的な誤りを指摘したり訂正したりすることはしない。したがって、調音の
方法や場所を示しながら適切な音声モデルを提供することは、教員の大切な
役割だと言える。
ウ 理解を助ける英語、確認する英語
これは、聞いたり読んだりした内容について、目的に応じた理解ができてい
るかどうか確認したり、理解を促進したりするために使う英語である。
説明のためのTeacher Talk や WH疑問文などを用いた質問・応答がこれに
当たる。
エ 言語活動を成功に導くための英語
学習の主体は生徒であり、授業においては教員以上に生徒が英語を使う機会
がなければならない。そのためには、適切な言語活動、特に、コミュニケー
ションを図る言語活動が授業の中心となるような指導が行われなければなら
ない。
教員には、教科書の内容を素材として、その素材に適した言語活動を工夫す
ることが求められる。必要に応じて、文法を言語活動と効果的に関連づけて
指導することも求められる。
これらを効果的に行うための一連の準備を一人の教員が担うことは大変であ
る。同じ学年を担当する教員が協力して行うことが大いに期待される。
言語活動をさせる際には、生徒が思いつかなくて活動が行き詰まっている英
語表現を提示するなど、つまづきを乗り越えられるよう適切な助言をして、
活動に従事しているすべての生徒が達成感を味わうことができるように配慮
しなければならない。毎時間繰り返される言語活動が生徒にとって失敗の連
続になってしまうようでは、英語学習への動機付けができないからである。
オ ほめる英語、動機付けをする英語
どんなに学習が進んでも、自分の英語力に自信を持てる生徒は少ない。なぜなら、
英語は外国語であり、進歩の状況が自分ではわかりにくいものだからである。
そのような学習者に対して動機付けをし、その動機を維持させるためには、生
徒が英語を使ってできたことやできるようになったことを明らかにして、ほめ
る必要がある。そのため、教員には意図的かつ積極的にmotivation feedback
をすることが求められる。
(2) 授業の実践に当たって気をつけてほしこと
ア 生徒の理解の程度に応じた英語を使うこと
生徒の理解を超えた英語は、どれだけ聞かせても英語によるコミュニケーショ
ン能力の育成にはつながらない。言語習得に必要な適切なインプットにならな
いからである。
教員は、生徒の表情や質問に対する応答から、理解の状況を把握し、必要に応
じて、話す速度を落としたり、優しい表現に言い換えたり、例示をしたり、黒
板に絵を描いたり、実物を示したりするなどして、生徒が耳にした英語を推測
しながら概ね理解できるようにする必要がある。
理解に「あいまいさ」が残る場合には、不安に感じる生徒もいると思われる。
そのような生徒に対しては、外国語はあいまいさに耐えながら曖昧さを減じて
いく営みであるから心配しなくてもよいことを伝えて、安心させる必要がある。
また、仮に、日本語を聞いて英語が理解できたつもりになっても、それは英語
ではなく、日本語を理解しているに過ぎない場合が多いということも伝える必
要がある。英語を理解させるためには絶対に日本語が必要だという誤解が生じ
ないような指導が大切なのである。
イ 教員が話しすぎないこと
学習の主体は生徒である。「授業は英語で行うことを基本とする」とは言って
も、授業時間のほとんどを教員が話しているようでは、生徒が英語を使う場を
奪ってしまうことになる。授業には、生徒が、分かる英語に触れる機会
(exposure)と生徒がコミュニケーションの手段として英語を使う場合
(experience)がバランスよく盛り込まれていなければならない。
ウ 動機付けを意識した授業をすること
授業は動機付けの場、動機を持続させる場であるとも言える。本時の授業で、
生徒の学習意欲を喚起することができたのか、もしかしたら、意欲を減退させ
てはいないかという視点から授業を振り返り、必要な改善を図ることが求めら
れる。
エ 学習的な言語活動とコミュニケーションを図る言語活動のバランスを考え
ること
教員や音声教材を手本にして徹底的に音声練習をしたり、ディクテーションを
したりするなど英語そのものの改善を目的にした学習的な言語活動と、要約を
伝えたり自分の意見を述べたりするなど、英語を使ってコミュニケーションを
図ることを目的にした授業をバランスよく設ける必要がある。その割合は、生
徒の実態に応じて変えるべきものであり、一律に示すことはできない。
オ 親和関係を構築すること
コミュニケーション能力を育成する教室には親和関係が生まれる。また、親和
関係が存在しなければ、コミュニケーション能力の育成はうまくできない。
教員の英語に対する熱い思いや英語に接することの喜びを態度に示しながら、
生徒一人一人の学びを大切にする指導を持続することによって、教室に信頼と
尊敬が生まれる。
そのような教室には、失敗が許し合える雰囲気が生まれ、生徒の自発的な発言
を引き出しやすい環境になる。言語活動に最適な環境が創られるのである。
(前略)
生徒は、間違った時、教師に質問してくる。「え、何で間違っているんですか」、
「先生、これどう考えたらいいんですか」と生徒が言った時、「前に説明した
はずだけどな~」と言えば、ノートを開いて必要な情報を探し始める。
それが、板書を写させる意味だということがわかるまで何年かかったであろうか。
つまり、板書はteacher-centeredな授業ではなく、student-centeredな授業でこそ、写した価値が出てくる。間違うからこそ学習は深まる。間違うからこそ理解が深まる。英語はそういう教科である。
(中略)
さらに、面白いことに、生徒はノートを見て自分のミスに気づき、訂正したものが
合っていたら、「よっしゃ、正解。やったぜ」などと喜色満面で言うのである。
つまり、訂正できたのは自分の手柄だと思うのである。
前述の例で言うと、私が「He playing tennis、ではなく、He is playing tennisだろ」と言うと、生徒は「あ、本当だ」と言って消しゴムを使うけれど、
実はこの時、頭も心もほとんど動いていないので、同じミスを繰り返す。
一方、「何か抜けているぞ。12月に写したノートを見てみ」と言うと、生徒はその
ページを開き、板書を写したものを読むうちに、「あ、分かった、isが抜けていたと
思って訂正し、
「先生、先生、Please check my answer again.」と私を呼ぶ。
「よし、分かったか?お、isが抜けていることに気がついたな。すばらしい!
マル!」
教師にそう言われたら、生徒は答えを自分の力で見つけたぞ、と誇らしい気持ちになる。
「そうだった、He is playing tennisだよな~」と分かった時、自分の字でノートに書かれた「現在進行形 公式:am/are/is + 動詞ing、意味:~している最中だ、しているところだ」という文字は、写した当時の何倍もの強烈さで生徒の脳に刻み込まれる。
これが「学習者心理」であり、「頭と心が動く授業である。」
「『(英語)授業改革論 田尻悟郎 著 pp 11-12』 教育出版 1,800円

信ずる者は救われる・・・まずは、書籍を読んで、「まねぶ」から「学ぶ」へ。
何度読んでも、いい味してますよ、この本は・・・。
生徒は、間違った時、教師に質問してくる。「え、何で間違っているんですか」、
「先生、これどう考えたらいいんですか」と生徒が言った時、「前に説明した
はずだけどな~」と言えば、ノートを開いて必要な情報を探し始める。
それが、板書を写させる意味だということがわかるまで何年かかったであろうか。
つまり、板書はteacher-centeredな授業ではなく、student-centeredな授業でこそ、写した価値が出てくる。間違うからこそ学習は深まる。間違うからこそ理解が深まる。英語はそういう教科である。
(中略)
さらに、面白いことに、生徒はノートを見て自分のミスに気づき、訂正したものが
合っていたら、「よっしゃ、正解。やったぜ」などと喜色満面で言うのである。
つまり、訂正できたのは自分の手柄だと思うのである。
前述の例で言うと、私が「He playing tennis、ではなく、He is playing tennisだろ」と言うと、生徒は「あ、本当だ」と言って消しゴムを使うけれど、
実はこの時、頭も心もほとんど動いていないので、同じミスを繰り返す。
一方、「何か抜けているぞ。12月に写したノートを見てみ」と言うと、生徒はその
ページを開き、板書を写したものを読むうちに、「あ、分かった、isが抜けていたと
思って訂正し、
「先生、先生、Please check my answer again.」と私を呼ぶ。
「よし、分かったか?お、isが抜けていることに気がついたな。すばらしい!
マル!」
教師にそう言われたら、生徒は答えを自分の力で見つけたぞ、と誇らしい気持ちになる。
「そうだった、He is playing tennisだよな~」と分かった時、自分の字でノートに書かれた「現在進行形 公式:am/are/is + 動詞ing、意味:~している最中だ、しているところだ」という文字は、写した当時の何倍もの強烈さで生徒の脳に刻み込まれる。
これが「学習者心理」であり、「頭と心が動く授業である。」
「『(英語)授業改革論 田尻悟郎 著 pp 11-12』 教育出版 1,800円
信ずる者は救われる・・・まずは、書籍を読んで、「まねぶ」から「学ぶ」へ。
何度読んでも、いい味してますよ、この本は・・・。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新コメント
[07/23 その他の世界一流スーパーコピー]
[03/11 安達克佳]
[03/10 児玉陽子]
[11/11 replique van cleef & arpel]
[01/03 安達克佳]
最新記事
(05/06)
(03/31)
(02/19)
(01/30)
(12/31)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
あんときのワタリ
年齢:
67
HP:
性別:
男性
誕生日:
1957/06/08
職業:
函館市立西中学校 校長
趣味:
スノボ 水泳 カラオケ
自己紹介:
平成22年度4月から函館市中学校英語教育研究会会長に就任いたしました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ブログ内検索
最古記事
(06/11)
(06/23)
(06/23)
(06/23)
(06/25)
P R
カウンター
